
今回はC.A.B. M+を使い、内蔵されてるキャビタイプのVirtual Cabと、外部からダウンロードして取り込んだIRを鳴らしてみました🤘✨
IR編
まずIRなんですが、これは実質失敗です(爆
というのは、
・ギター
・BOSS DS-2
・C.A.B. M+
・モニタースピーカー
と繋いでおり、本来ならばディストーションエフェクターであるDS-2とC.A.B. M+の間にプリアンプを挟まなければならないのを怠ってるからです😅
なのでキャビタイプも直感的に「マイクが極めてスピーカーに近く、低域を拾えてない」.wavファイルを選んでしまっており、キャビシミュを殆ど活かしきれてない音になってます。
しかしながら、DS-2の音の変わり様が分かるようにはなってるので、参考になればと思い貼っておきます(笑
逆に言えば、ディストーションエフェクターとキャビシミュだけでも、低域がスポイルされたキャビタイプを選べば何とかギターサウンドらしい音をモニタースピーカーから鳴らせるという事でもあります(笑
(好き嫌いは別れるけど、個人的にはわりと好きw)
キャビタイプはリンク先のYouTubeの概要欄に書いてます。
Virtual Cab編
今度はディストーションエフェクターとしても、プリアンプとしても、ラインドライバーとしても使えるGOAT Generatorを使い、DS-2同様そのままC.A.B. M+に接続してMSP-3を鳴らしてみました。
キャビタイプはIR編同様、YouTubeの概要欄に書いてます。
個人的な感想としては、C.A.B. M+をバイパスしたGOATのオリジナルの音と比べ、オリジナルに準じてるようなものから、かなりサウンドが改変されるものまであり、やはりキャビネットのエンクロージャーの材質やスピーカーの種類によって、頑固に癖の強いGOAT(Rockman)の音色も変わるんだなと感じました(笑
またベースアンプはGreen 18のように全く不向きなものから、Heaven Topのようにそこそこ使えるものもあり、エフェクターさえ揃えればベースアンプにギター繋いでも良い物もあるという事が分かりました(まあベース用の方のパス10にギター繋いで良いサウンドが出るって言われるしねw)
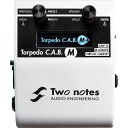
- 価格: 44000 円
- 楽天で詳細を見る
アナログか?IRか?
さて、話変わって今度はキャビシミュにおける、アナログ仕様とIR仕様(デジタル)について、お話を伺ってきたので記事にします✍
まずアナログ仕様は、代表的なものにTech 21 SansampシリーズやPalmerのPDI-03、AMT Legend Ampシリーズ、A/DA GCSシリーズ、Hughes&Kettner Red Boxなどの定番から、Suhr A.C.E.といった新鋭のモデルなどが挙げられます。
これらは全てアウトプットの直前にフィルターEQがあり、それがギターアンプから出したようなサウンドになるように高域と低域をバッサリとカットし、ミキサーなどに直接送れるようになってます。
各々のメーカーによってそのイコライジングの仕方は異なり、GCSやSansamp Classic、Red Boxのようにプリセットになってるものから、A.C.E.のようにある程度リニアに音を変化させられるものまで様々です。
アナログ仕様の最大の利点は「レイテンシーが全く無い」という事です。
IRは、ファイルによっては最初にコンマ数秒の無音部が時折あり、これがまずレイテンシーを引き起こします。
またハードウェアや、ソフトウェアの場合はPCの処理能力の遅さでもレイテンシーに繋がる場合もありますが、アナログのキャビシミュはそのまま信号がフィルターEQの回路を通っていくだけなのでレイテンシーという概念がありません。
ではIRに比べ何が劣ってるか?となると、やはりEQの処理のみなので、スピーカーの空気感とかも全てキャプチャリングしてるIRの.wavファイルに比べるとどうしても平坦になって無機質な感じになりがちです。
「このアナログのキャビシミュを通して、ミキサーやモニタースピーカーに出力した音が好きなんだ!」
という人のためのものという印象ですね。
Sansamp (Flyrig)シリーズやAMT Legendシリーズ、Apex Preamp、Rockman (X100、Sustainor、Distortion Generator、XPR)、GOAT Generatorなどはアナログのキャビシミュが一体型になってるので、アンプ要らずで単体でミキサーに直で行けるという便利さがありますし、それらのキャビシミュも中々よく出来てます👍✨
続いてデジタルのIR(Inpulse Response)仕様ですが、こちらはアンプを繋いだ状態のキャビネットから出た信号をマイクで拾い(凡そ40〜100ms)、それを.wavファイルにしたものが元になってます。
そしてそれをTorpedo C.A.BやMooer Rader、Line 6 HelixなどのIR対応機種に保存し、.wavファイルの信号音声を、前段のプリアンプに加えてミキサーやモニタースピーカーなどに出力します。
これの最大のアドバンテージと言えば、やはりスピーカーの空気感、奥行感などが忠実に再現される点です。
YAMAHA MSP-3のような3インチのモニタースピーカーからでも、IRによっては12インチ4発キャビの迫力などが堪能出来ます!
IRは有料無料様々なものがあり、中にはCelestionplusなど公式が出してるIRもある為、選択肢は無限にあります(勿論機材があれば自分で作る事も可)
アナログでは再現出来ない部分を大まかに賄ってるので、昨今のレコーディングではこちらが主流です。
しかしながら万能という訳でもなく、やはり幾つかの欠点もあります(笑
まず前回の記事でも書いた通り、D/Aコンバータの品質でそのIRの再現度が超変わります。
次に前述の通り、あらゆる点でレイテンシーが発生する場合があります。
「.wavファイルの先っちょの無音部をカットして作り直せば良いのでは?」
と、そんな風に考えてた時期が俺にもありましたが(笑)、これをやると音が変わります🥶
最初の無音部にもしっかりと信号が発生してて、それを含めて完成されてるIRなので、たとえ無音部でもカットしてしまうと全体のバランスが崩れるみたいです。
そしてこれも中々厄介な事象なのですが、撮るマイクやそのマイクの位置でも音が超変わるので、
「マイクは○○製でスピーカーからの距離2cm」
「マイクは✕✕製でスピーカーからの距離4cm」
といった風に、その都度個別にファイルを作成して行かなければなりません。
なので、自分が気に入ったIRを選別して保存する必要があります(Torpedo C.A.B. M+に入れられるIRは最大25個)
またTorpedo C.A.B. M+の場合、IRではない「Virtual Cab」モードだとマイクの種類やスピーカーからの距離などを細かく設定出来ます。
IRと遜色ない音質なので、もし気に入ればこちらを駆使して音作りするのもいいかもしれませんね(公式の説明だと、内蔵の他に追加で購入出来るみたいです)
Torpedo C.A.B. M+はハードウェアに拠るレイテンシーやD/Aコンバータの品質などIRのキャビキミュにおける重要な点においては全て高水準でクリアしており、至極個人的にはIRの入門として最適だと考えてます(安物買いの銭失いという言葉があるように、下手に安価な物を買うより、総合的にハイスペックなコレを最初に買っておけば買い足す必要が無くなる為です😉)
最後に
オーバードライブやディストーション、ファズなどの「エフェクター」を使いたい場合、必ずキャビシミュとの間にプリアンプを挟みましょう(笑



