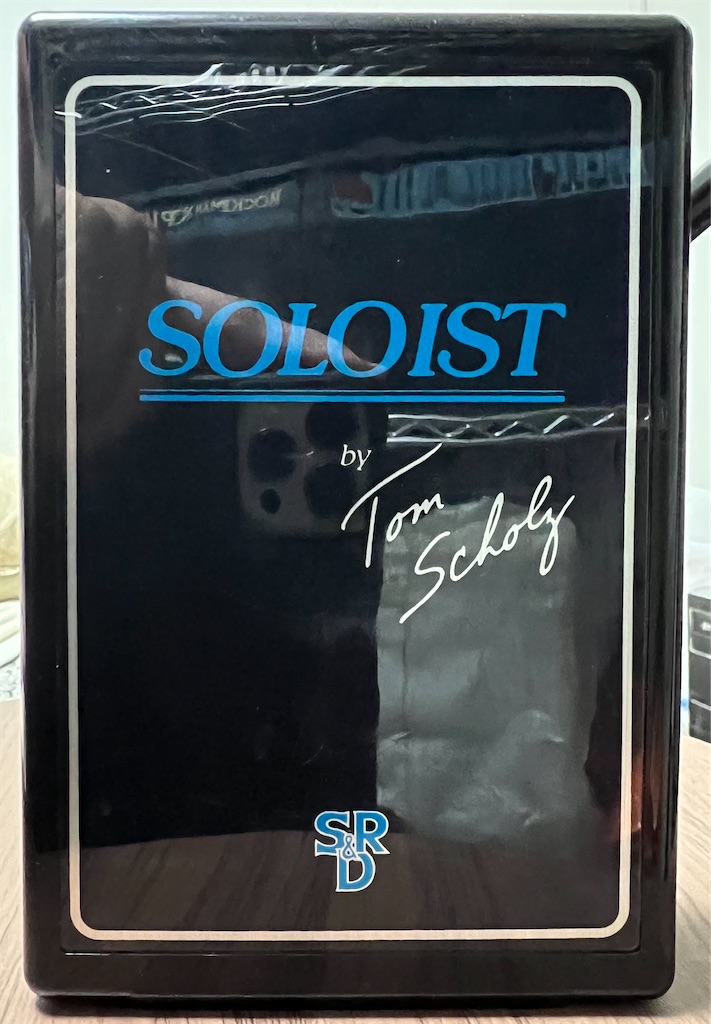続いてmy new gear第二弾!
Rockbox Brown Sugarです!
「Brown」付いてるのでブラウンサウンドなのか?と訊かれたら、公式サイトではそれを匂わせるニュアンスで説明されてます笑
「英国製のマスターボリューム無しの、ハードロックなどで活躍したフルスタックのアンプの再現」
とあるので、どう考えてもMarshall 1959 Super Leadか1987Xです、本当に(ry
Rockboxはカリフォルニア州サンノゼに構えるペダルビルダーで、主に歪系のラインナップが多く、その他にコンプレッサーやコーラスなども作ってます。
1971年から楽器屋で働き、同時にミュージシャンでもあったChris Campbell氏によって設立され、様々なアーティストの広告などを手がけ、それと同時に交流を深め、その一流のミュージシャン達がどんな音を求めてるかという事を詳しく聞き、それをエンジニアと共に製品に落とし込んでペダルをリリースしてきたというのが経緯だそうです。
ペダルの筐体は同じ形に統一されており、フロントパネルから丸く曲げて下部側面を形成してる独特な形状となってます。
インターフェース
Volume、Gain、Tone、Contourの4つのつまみで構成されてます。
シールドやアダプタージャックは筐体上部側面に統一されており、MXRやBOSSなどと併用する場合は少し煩わしいと思いました。
電源は一般的なエフェクター用アダプターで作動します。
トーン
まずGainですが、12時を基準に歪量が大きく変わります。
左に回すと極端に歪量と低音が減る感じで、0にすると音が消えます。
オーバードライブとしてはまずまず使える印象でしょうか。
12時より右に回すと低音が付与され、迫力のあるハイゲインディストーションサウンドが得られます。
倍音成分や特有の角の取れたエッジはチューブアンプっぽい歪という印象で、トランジスタアンプでもチューブアンプで歪ませたようなサウンドが得られます。
Toneは高域成分の増減と音量に作用し、特に音量が顕著に変わるので、最初から固定のセッティングで使うなら兎も角、都度セッティングする場合はVolumeとの相互調整が必須ですね。
扱ってる帯域は凡そ4kHzでQは狭く、下げればモコモコ、上げればザクザクキンキンな高域になります。
Contourは凡そ1〜2kHz辺りの、Qが比較的広めなハイミッドを増減させます。
12時より左に回すとハイミッドが凹んで相対的に500Hz辺りが強調され、モコモコしたサウンドになります。
逆に右に回していくと音が明るくなり、同時に密度の高い歪が出てきます。
個人的には12時を基軸として、右にちょっとずつ回して明瞭さを調節するのがいいかなと思いました。
総評
AIABとしては相当レベルが高く、各種トーン調整は様々なチューブアンプの歪み方を色々再現してるなと感じました。
Lovepedal Jubileeも中々のチューブアンプの再現度だなと感じたので、最近のAIABは優れてるものが多いとひしひしと感じました😂
Marshall系のナチュラルな歪をペダルで得たい場合、コレはかなりオススメです👍✨